演劇には映画やテレビと違って、役者と観客の間に暗黙のルールが存在する。俳優が舞台に立って「星が綺麗だな」といえば、観客は懸命になって綺麗な星をイメージしなければならない。
以上を、苫米地 英人 (著)『苫米地英人コレクション1 洗脳護身術』86ページより引用させていただきました。
タモリさんが人が急に歌い出すのはあり得ないからミュージカルは嫌いだというのは有名ですが、あれとこれって似ている気がする。
普通はミュージカルで登場人物が歌い出すと頭の中を切り替えます。
だって人が突然歌い出すのは日常生活ではあり得ないからです。
なので普通は自分で頭を切り替えて、歌は登場人物の心の声を聴いているのだと自分に言い聞かせます。
ミュージカルで俳優が歌い出せば、頭の中が自動的にモードが切り替わる。
外面ではなく内面を見るモードに切り替わる。
そうでなければ人が突然歌い出すことに違和感を覚えて感情移入ができなくなってしまう。
紙芝居も同じです。
紙芝居という静止画モードを自分の頭の中で動かして動画モードとして処理するから紙芝居に感情移入することができる。
言葉では走っていると言ってるけど絵は動かないじゃん!では紙芝居にはならない。
頭のモードを切り替えないと紙芝居も楽しめない。
映画やテレビは受け身でいいけど、演劇になると能動性が必要になってくる。
自分でいろいろと想像力を働かさないと置いてけぼりをくらうことになる。
インプットされる想像と自分でアウトプットする想像、その違いがある。
イメージを植え付けられるのか、自分でイメージを創造するのかの違いだ。
どちらの態度が洗脳と闘えるか明らかだ。


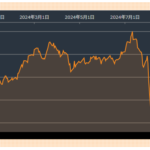

コメント